【ヘルスセキュリティセンター兼任教員・専任教員】
 |
中川 一路 (医学専攻 微生物感染症学 教授) ➡種々の病原性細菌のゲノム情報解析を通じてそれらの病原性獲得機構と進化の道程を明らかにすると共に、細菌の宿主細胞内での動態を分子レベルで解析することにより、細菌感染症に対する新規予防法や治療方法を確立することを目標としています。これら細菌、宿主の両面同時に情報、実験を駆使するハイブリッドアプローチで取組んでいることが本研究室の特徴です。 |
 |
上野 英樹 (医学専攻 免疫細胞生物学 教授/ 高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点 副拠点長/ 免疫モニタリングセンターKIC センター長) ➡ヒト検体を用いたヒト免疫学研究を30年弱に渡り行ってきました。現在はヒト感染症免疫、ワクチン免疫応答、ヒト肝臓での免疫応答、がん免疫などを中心に、主にヒト臓器検体を用いたシングルセルレベルでの多次元解析を行っています。また次世代パンデミックへ備えるためのヒト免疫データベースを構築しています。 |
 |
青山 朋樹 (人間健康科学系専攻 専攻長 / 運動機能解析学 教授) ➡パンデミックや大規模災害から元の生活に復帰するためにはさまざまなインフラの復旧と共に、低下した体力や生活機能力を回復しなければなりません。これは必ずしも疾病の罹患や外傷がなくても通常と異なる生活を強いられることで生じる機能低下ですので、パンデミックや大規模災害の期間中だけでなく、その前から個人も医療システム、行政も備えておく必要があります。 |
 |
塩見 美抄 (人間健康科学系専攻 地域健康創造看護学 准教授) ➡政令市保健師としての実践経験があり、研究では、行政保健における地域アセスメントや住民ニーズに基づく事業化・施策化のモデル開発・教育プログラム開発に取り組んできました。健康危機発生時は、平常時の実践課題が増幅され、問題が深刻化・長期化することが多いため、健康危機発生時に限らない地域保健行政における実践の向上・開発を目指してまいります。 |
 |
長尾 美紀 (医学部附属病院 臨床病態検査学 教授) ➡臨床系の教室として、薬剤耐性菌・ウイルスの微生物学的解析や臨床研究、新規検査系の開発を行っています。感染症対策は社会全体で取り組む必要があります。様々な分野の先生方と連携して、COVID-19のような流行性ウイルス感染症だけでなく、サイレントパンデミックと称される薬剤耐性菌の対策に貢献できるような研究を目指しています。 専門領域:感染症診療、感染制御、臨床検査 |
 |
松村 由美 (医学部附属病院 医療安全管理部長 / 医療安全管理学 教授) ➡医療に起因する、回避可能な害を可能な限り低いレベルにとどめることを目的として、診療プロセスの改善に取り組む。医療は人で成り立つものであり、働きやすく、心理的安全であることが、よいパフォーマンスにつながると考え、働きにくさの改善に取り組む。安全のために行っている習慣(ダブルチェック等)の科学的根拠について研究テーマとしている。 |
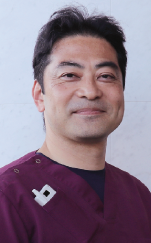 |
大鶴 繁 (医学部附属病院 救命救急センター長 / 初期診療・救急医学 教授) ➡医学生時代に阪神淡路大震災を被災し救急医を志す。新潟中越地震、東日本大震災への災害医療派遣を経験。2016年に京大防災研と同医学部附属病院とが連携して、多職種連携・分野横断で京都iMED防災研究会を組織。熊本地震への調査結果から『災害時の医療継続』をテーマに、2018年に防災研に地域医療BCP連携研究分野を開設し、地域医療継続計画(BCP)策定の実現により、健康危機に強い社会づくりを目指している。 |
 |
加藤 源太 (医学部附属病院 病床運営管理部 部長 / 診療報酬センター 特定教授) ➡救急医療、医療社会学、医療政策に関与した経験に基づき、病院内の病床配置適正化や、高度急性期医療を担うケアユニットの機能再編を担当しており、現場と日々情報共有しながら、病院機能の向上に努めています。主な研究テーマは、国が所有する大規模医療データの利活用推進であり、個別研究や各種データの連結解析、海外動向の調査など、様々な角度から研究を行っています。 専門領域:医療政策、病院運営、医療社会学(専門職論) |
 |
牧 紀男 (防災研究所 社会防災研究部門 教授) ➡阪神・淡路大震災以降、災害対応・復旧復興、危機管理に関する研究を行ってきており、多くの自治体で危機管理、防災計画策定に関わっております。ヘルスセキュリティーについては医学部附属病院の先生方と研究会(iMED)を行っており、その成果をもとに防災研究所に地域医療BCP連携研究分野を設置しました。現在、災害時の医療サービスの継続性性能(レジリエンス)評価手法の開発を行っています。 |
 |
畑山 満則 (防災研究所 附属巨大災害研究センター 教授) ➡時空間情報を効率的に処理できる地理情報システムを核とし、総合防災システム、総合減災システムを確立するために求められる情報システムに関する基礎研究を行うとともに、行政・民間企業・地域防災を担うコミュニティ・災害支援ボランティア組織などを対象に、多種の自然災害における災害対応を想定した情報システムの構築方法論と評価手法を構築することを目指しています。 |
 |
谷 直起 (経済研究所 准教授) ➡公共政策が人口動態や企業行動等に与える影響を説明する理論モデルを構築した上で、企業や個人消費のデータを用いてシミュレーションを行い、あるべき政策を示す研究をしています。また、近年注目されているEBPM(証拠に基づく政策立案)に関連して、行政機関との実装プロジェクトも進めており、財務省とは格差の実態に関する分析を共同で実施している他、高知県とは、結婚・子育て政策の支援に向け、婚活マッチングシステムのデータ分析とシステム改善を進めています。また、同県及び三井住友カード株式会社と共同で、同県の観光政策をキャッシュレス決済データを用いて評価するプロジェクトを進めています。 |
 |
内田 由紀子 (人と社会の未来研究院 院長・教授) ➡京都大学人と社会の未来研究院 院長・教授。専門は社会心理学・文化心理学で、国際比較文化の実証研究から、ウェルビーイング、対人関係、感情などの研究を行う。 社会活動として、内閣府幸福度の日本の幸福感の指標作成、教育振興基本計画のWell-Being概念導入にも従事。日本社会心理学会理事、APS (Association for Psychological Science)理事。 |
 |
橋口 隆生 (医生物学研究所 ウィルス感染研究部門 教授) ➡蛋白質構造を原子レベルで可視化する技術を用いることで、小児ウイルス感染症と高病原性ウイルス感染症における病原性研究と創薬研究を行っております。特にウイルスの細胞侵入メカニズムや感染阻害分子によるウイルス侵入阻害の作用機序解明とワクチン抗原デザインに取り組んでおります。 |
 |
中山 健夫(社会健康医学系専攻 健康情報学 教授) ➡研究室の特色は下記の通りです。・健康・医療問題の解決を支援する情報のあり方を追求。・情報を「つくる・伝える・使う」の視点で捉える。・対象は医療者に限らず、患者・介護者・支援者などの医療消費者・生活者全般。・個人から社会レベルの意思決定の支援を想定。・ゲノム情報の応用やデータマイニングに関する研究も実施。・Evidence-based Healthcare、情報リテラシー、e-ヘルス、マスメディアによる健康・医療情報、情報倫理などの教育・研究を推進。 |
 |
近藤 尚己 (社会健康医学系専攻 社会疫学 教授) ➡貧困や孤立等、健康に影響する社会的な要因の実態解明やそこから生じる健康格差を是正するための政策やサービスの開発を目指しています。災害時は健康格差が拡大することが知られています。災害時に影響を受けやすい人々に対して平時より求められる対策やしくみの開発も進めています。 |
 |
石見 拓 (ヘルスセキュリティセンター 教授 / 社会健康医学系専攻 予防医療学 教授) ➡循環器、救急蘇生、予防医療・健康増進領域を中心に、臨床研究、疫学研究を行っています。特に、普及と実装科学研究に力を入れており、市民による心肺蘇生やAED使用の効果検証、救命教育プログラムの作成と教育効果の検証、これらの取り組みの普及による地域における救命効果の検証、PHR(パーソナルヘルスレコード)を活用した病気の予防や健康増進、救急災害時の活用を実現するための基盤構築に関わる研究などを進めています。 |
 |
久保 達彦(ヘルスセキュリティセンター 健康危機管理多分野連携学 教授 / 防災研究所兼任)(広島大学併任) ➡多種多様な組織が同時に活動する健康危機管理においては関係ステークホルダー間の多分野連携体制を平時からの連続性をもって戦略的に仕組み化しておく必要がある。容易ならざるこの課題に挑むべく、本分野ではマルチセクター/マルチステークホルダー間をつなぐ情報サイクルの構築を通じて多分野連携を実現し、もってオールハザードアプローチに基づく健康危機情報管理、健康危機体制管理を実行する技術/制度/政策について研究する。必然として、研究は学術領域や国境の壁を超えて推進する。また国際緊急援助分野で活躍できる人材の育成を目指す。 |
 |
西浦 博 (ヘルスセキュリティセンター 健康危機管理情報解析学 教授 / 社会健康医学系専攻 環境衛生学 教授) ➡健康危機時の感染症流行や病原体のリスクアセスメント、情報解析とその結果の伝達に関して集中的に学びます。大規模な感染症の流行が起こる前から動物等が保有する病原体のリスクを理解し、また、流行リスクに対するヒトの行動(例えば、移動や接触)の影響とその制御の影響分析を行います。 |
 |
今中 雄一 (ヘルスセキュリティセンター 健康危機管理システム学 教授 / 社会健康医学系専攻 医療経済学 教授) ➡医療システム(保健医療介護)の質・効率・公正、人々が健康になる社会の研究を基盤に、健康危機に対する、医療システム、社会・地域・組織のレジリエンスの研究開発を展開します。災害等の突発的な危機に加え、社会保障の脆弱化など静かに迫る危機も対象とし、予防・準備、対応、復旧・復興のしくみづくりを領域横断的に視野に入れます。人材育成において実践現場と連携し専門的な実践力の強化を図ります。 |
|
【客員教授】 |
|
冨尾 淳 (国立保健医療科学院 健康危機管理研究部長) |
|
國井 修 (公益社団法人 グローバルヘルス技術振興基金 CEO) |
|
齋藤 智也 (国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 感染症危機管理研究センター長) |
|
佐々木 昌弘 (厚生労働省 危機管理・医務技術総括審議官) |
|
近藤 久禎 (国立健康危機管理研究機構 DMAT 事務局 次長) |
|
【特任教授】 |
|
福島靖正 (前厚労省医務技監) |
【ヘルスセキュリティセンター運営委員会】
** 副センター長